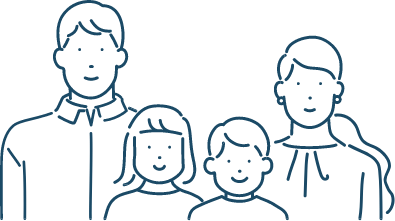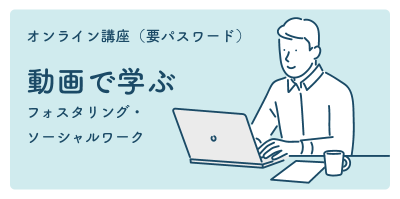お知らせ
- 2023年度 立命館大学人間科学研究所年次総会 「子ども家庭支援のネクストステージ」のお知らせ(2024-02-05 14:36:42)
- 2023年度の講座がはじまります(7/2開講式)(2023-06-27 00:00:10)
- 2023年度の募集を終了しました(2023-06-26 00:00:07)
- 2021年度3期生の修了式を行いました(2022-07-11 17:01:33)
- 公開シンポジウム7/6(水)10:00〜12:00「里親と実親の協働について」を開催します!(2022-06-23 19:37:49)
- フランスのフォスタリング支援を学ぶスタディツアー(2022-03-14 10:10:15)
- 二期生の修了式を行いました(2022-03-14 10:09:17)
- フォスタリング・ソーシャルワーク専門職講座 シンポジウム「里親のピアサポートを考える」(2021-06-29 15:23:31)